
以前、このサイトでは行商について解説をしました。
古物商許可を取得すると許可証が交付されることになります。この許可証は、古物商許可を取得した者であることを証明するものであり、古物の取引の安全を相手に示すものですから非常に重要な役割を果たしています。 とはいえ、営業所で古 …
行商とは、営業所以外の場所で取引を行うことをいい、許可申請の時点で行商を行う旨を申告をすれば、古物営業を行う古物商や古物市場主は行商をすることが認められています。
しかし古物営業法では、営業場所に制限が設けられており、どんな場所でも古物営業を行えるわけではなく一定の場所では取引ができないことになっています。
この営業の制限をきっちり理解しておかないと、気付かないうちに違法な場所で取引を行ってしまう可能性があります。
そんなことにならないために、古物商と古物市場主における営業の制限について確認していきましょう。
古物商の営業の制限
古物営業法14条1項(平成30年改正 ただし~)
- 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはならない。(※ここから追加)ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りではない。
この規定により、原則として古物商はたとえ許可証を携帯していたとしても、営業所もしくは取引相手の住所、居所以外の場所で古物商以外の者から、古物の「買い受け」、「交換」、「売却・交換の委託を受ける」ための受取りをしてはいけないことになります。
これは、営業所または取引相手の住所もしくは居所以外の場所において古物の取引をする場合には、法令に定められた各種義務の確実な履行が期待できないために設けられた規定です。
なお、古物商が営業の制限に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。 これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。 古物営業法の目的についてはこちらで詳しく解説しています。 法令で定 …
平成30年10月24日から営業制限が一部見直されました!
平成30年10月24日から改正された古物営業法が施行され、営業制限が見直されました。
上記の通り、原則として古物商は営業所または相手方のまたは居所でしか買受等のための古物を受け取ることはできませんが、事前に公安委員会に日時、場所を届け出ることで営業所以外の仮の店舗(仮説店舗)においても古物を受け取ることができるようになりました。
よって、これまで露店などの営業所以外の店舗では売ることしかできなかった場所で買取りができるようになったというわけです。
仮設店舗
仮設店舗とは、例えば百貨店などにおけるイベント会場のことです。
取引相手が古物商ならどこでも取引できる!
上記の条文をよく読むと、「古物商以外の者から・・・・・・・受け取ってはならない。」とされています。
したがって、取引相手が古物商であれば、「買い受け」、「交換」、「売却・交換に委託を受ける」ための受取りは、どんな場所でも可能になります。
たとえば、相手が古物商であれば、コンビニの駐車場で古物の受け取りをすることもできるということになります。
ちなみに、この後に解説しますが、古物の「引渡し」については制限がありませんので、相手が古物商であろうがなかろうが、どこでも可能ということになります。
あくまで制限されているのは「受取り」だけ!
上記の条文の最後の文言では、「受け取ってはならない」となっています。
つまり、「引渡し」については、行商が認められている古物商であれば、どこの場所でも相手が古物商でなくてもできるということになります。
たとえば、相手が古物商でなくても行商をすることが認められていれば、コンビニの駐車場にて古物を売却し、相手に古物を引き渡し、それに対してお金を受け取ることも可能ということになります。
(あまりお勧めできる取引方法ではありませんが…)
古物市場主の取引の制限
古物営業法14条3項
- 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
つまり、古物商でない者は古物市場に参加できないということです。
これは、古物市場では一度に大量の古物が取引きされることから、古物商以外の者により盗品等の処分の場として利用される恐れがあるため、古物市場においては古物商同士の取引以外の古物の取引を禁止しているのです。
なお、古物市場主がこの取引制限に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。 これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。 古物営業法の目的についてはこちらで詳しく解説しています。 法令で定 …
まとめ
いかがでしょうか?
ややこしい内容だと思いますので、簡単にまとめておきます。
【行商ができる古物商が一般人と取引するケース】
| 場所 | 買取 | 売却 |
|---|---|---|
| 営業所 | 〇 | 〇 |
| 相手方の住所・居所 | 〇 | 〇 |
| 仮設店舗 | 〇 | 〇 |
| フリーマーケット | ✕ | 〇 |
| 古物市場 | ✕ | ✕ |
フリーマーケットで古物商が営業目的ではなく自己消費のための買い物(買取)をすることは可能です。
【行商ができる古物商同士が取引するケース】
| 場所 | 買取 | 売却 |
|---|---|---|
| 営業所 | 〇 | 〇 |
| 相手方の住所・居所 | 〇 | 〇 |
| 仮設店舗 | 〇 | 〇 |
| フリーマーケット | 〇 | 〇 |
| 古物市場 | 〇 | 〇 |
古物は売却するときよりも、買い受けるときの方が規制が厳しく果たすべき義務も多く存在しています。これは、盗品などが市場に流入しないようにするという「防犯」のために他なりません。
行商ができるからといって、どこでも、誰を相手にしても買取りができるわけではありません。このことを十分に理解した上で、適正な古物営業を行ってください。





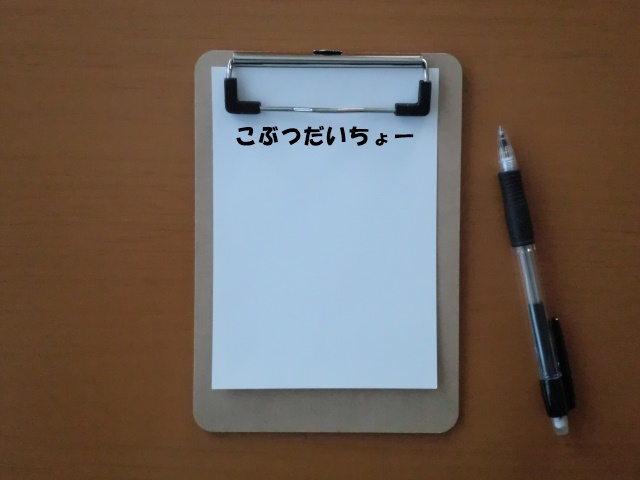




メールで完結!個人申請が好評です!
愛知県の古物商許可申請なら
愛知古物商許可.comにお任せください!
愛知県の古物商許可申請代行サービスをご利用いただけます。
面談不要!メールのやりとりだけで簡単に古物商許可が取得できます。(FAX・郵送でもOK)
メールで完結するから忙しい方におすすめ。特に平日は仕事をされている個人様から好評です!もちろん法人申請も対応可能!
<古物商許可申請>
ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ!