
古物営業法には、古物商または古物市場主の相手確認義務が明文で規定されており、盗品の古物市場への流入を防止するために非常に重要な義務とされています。
なぜ古物営業を行うために許可が必要なのかというと、それは「防犯」と「被害の迅速な回復」のためです。もし盗まれたものが簡単に古物流通市場に流入してしまうと、これらの目的を達成することはできません。 そこで、古物営業法は古物 …
一方で、古物競りあっせん業者においては相手確認はあくまで努力義務とされています。
今回は、古物競りあっせん業者の相手確認について解説します。
相手確認の努力義務
復習になりますが、古物競りあっせん業者とは古物営業の1つで、いわゆるネットオークションを運営する古物営業のことです。3号営業とも呼ばれています。
おそらくあなたは、中古品を仕入れて販売をすることを「古物営業」というのだと考えているのではないでしょうか? 確かにそれは間違いではなく、紛れもなく古物営業に該当します。 しかし、それだけが古物営業ということではないことを …
古物競りあっせん業者は、古物を売却しようとする者から出品を受け付けようとするときは、その者の真偽を確認するよう努めなければならないとされています。
古物営業法21条の2
- 古物競りあっせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあっせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
これは、インターネット上の取引の匿名性をなくし、窃盗犯などによる盗品の売却を困難にするという狙いがあります。
出品者の確認のタイミングとしては、出品を受け付ける前に実施する必要があります。したがって、もし、古物競りあっせん業者が出品の申込みを受けた後すぐに出品を認める場合、本人確認のための措置を即時に行わなければなりません。
なお、努力義務を果たさなくても違反行為にはなりませんので、罰則規定もありません。
確認の方法
たとえば、相手の確認方法として以下のような方法があります。
- 住所、氏名、年齢を確認する
- 口座振替による認証
- クレジットカード認証(カード番号と有効期限の確認)
- 古物あっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者名義の預貯金口座に振り込むことを約する
- 2回目以降の取引をする出品者にIDとパスワードを入力させる
上記の措置をとれば、努力義務を果たしていると考えられます。
まとめ
いかがでしょうか?
実際のネットオークションでは、個人情報を登録した会員でないと出品できないようになっており、会員ページにログインするためにIDやパスワードの入力が求められていますので、きちんと努力義務を果たしているといえるでしょう。
努力義務とは「やらなくてもよい」ということではなく「やるべきこと」と考えてください。
古物競りあっせん業者はネットオークションの運営者として、たとえ法令上の義務でなくても自発的に利用者が安心して取引ができるような体制を整える必要があるといえるでしょう。
なお、古物競りあっせん業者は取引の記録についても努力義務となっています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
古物商または古物市場主は、その取引の内容を記録し3年間保存しなければなりません。これは、法律上の義務となっていますので違反すると罰則があります。 一方で、古物競りあっせん業者にも取引の記録についての規定はあるものの、古物 …


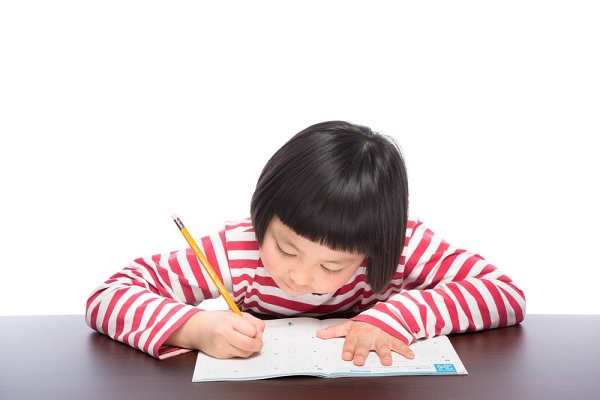



メールで完結!個人申請が好評です!
愛知県の古物商許可申請なら
愛知古物商許可.comにお任せください!
愛知県の古物商許可申請代行サービスをご利用いただけます。
面談不要!メールのやりとりだけで簡単に古物商許可が取得できます。(FAX・郵送でもOK)
メールで完結するから忙しい方におすすめ。特に平日は仕事をされている個人様から好評です!もちろん法人申請も対応可能!
<古物商許可申請>
ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ!