
古物商許可は、一般的に誰でも取得することが可能です。しかし、法令に定められた欠格事由に該当してしまうと、たとえ許可申請をしたとしても許可を受けることはできません。
許可を申請する前に欠格事由に該当しないかどうかを確認しておかないと、不許可処分をを受けてしまい、時間や手数料等がムダになってしまう可能性があります。
今回は、許可申請をする前に確認しておくべき欠格事由についてご紹介します。
欠格事由
古物商許可の欠格事由は、古物営業法4条に規定されており、次の各事項に該当する者は許可を受けることができません。
古物営業法4条(許可の基準)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可営業、虚偽申請、名義貸し等による罪若しくは窃盗、背任行為、遺失物等横領、盗品譲受等の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(※平成30年10月24日追加)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定された命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(※平成30年10月24日追加)
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業の廃止による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が欠格事項のいずれにも該当しない場合を除くものとする
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までの欠格事由のいずれかに該当する者があるもの
障害によって正常な判断ができない者や社会的信用のない者は古物商許可を取得できない!
障害によって、日常生活に必要な判断ができないと認められる者や、(※令和元年12月14日廃止)破産によって社会的信用を失っている者は欠格事由に該当し、古物商許可を取得することはできません。
また、法人申請の場合で、会社役員の中に判断能力に問題のある者や破産者がいると、その法人は許可を取得することはできません。
成年被後見人
昨今の終活ブームにより、成年後見制度という言葉が世に知られるようになりました。成年被後見人とは、その名の通り、後見人によって見守られている人のことです。
成年被後見人の制度は、民法によって次のように定められています。
民法7条(後見開始の審判)
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法8条(成年被後見人及び成年後見人)
- 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
精神上の障害によって日常生活を送るために必要な判断能力が無い状況にある人が親族等の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判を下すことで成年被後見人となります。
そして、成年被後見人の代わりとなって、成年被後見人のために意思判断をするのが成年後見人です。
成年被後見人となった者は、正常な判断能力な無いため、古物商許可を受けることはできません。(※令和元年12月14日廃止)
令和元年12月14日に施行された「成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴う関係法律等の改正」により、成年被後見人であっても古物商許可を受けられるようになりました。
被保佐人
被保佐人も、成年被後見人と同様、民法によって定められています。
民法11条(保佐開始の審判)
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
民法12条(被保佐人及び保佐人)
- 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
精神上の障害によって日常生活を送るために必要な判断能力が不十分である人が、親族等の請求により、家庭裁判所が保佐開始の審判を下すことで被保佐人となります。
成年被後見人と変わらないように見えますが、成年被後見人が「事理を弁識する能力を欠く~」に対して、被保佐人は「事理を弁識する能力が不十分である~」という点で、被保佐人の方が障害の程度が若干軽いことがお分かりいただけると思います。
しかしながら、適正に古物営業を行うための判断能力には達していないとされ、古物商許可を受けることはできないとされています。(※令和元年12月14日廃止)
令和元年12月14日に施行された「成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴う関係法律等の改正」により、被保佐人であっても古物商許可を受けられるようになりました。
破産者で復権を得ないもの
まず破産者とは、破産法によって以下のように定義されています。
破産法2条4項(要約)
- 「破産者」とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているものをいう。
破産とは、債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に返済することを目的とする裁判上の手続きのことで、裁判所によって破産手続き開始の決定を受けた者が「破産者」となります。
破産者は、経済的な信用を失っていることになるため、クレジットカードが使えなくなったり、一部の職業に付けなくなるなどの制約を受けることになります。
その制約の中の一つとして、古物商許可の欠格事由に該当してしまうのです。
「復権を得る」とは
「復権を得る」とは、破産者となることで受けていた制約から解放されることです。
次のような事由が発生した場合、破産者は復権を得ることができます。
破産法255条(復権)
- 免責許可の決定が確定したとき。
- 破産手続廃止の決定が確定したとき。
- 再生計画認可の決定が確定したとき。
- 破産者が、破産手続開始の決定後、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき。
破産者は、「復権を得る」ことで破産者ではなくなります。したがって古物商許可を取得できるようになります。
精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者は古物商許可を取得することはできない!
前述のとおり、令和元年12月14日からこれまで古物商許可の欠格事由に該当していた成年被後見人や被保佐人でも古物商許可を受けられるようになりました。
しかし、これはあくまで今まで門前払いであったものを個別に審査して許可の可否を判断するという方針に変更されたということです。
したがって、門戸は開かれたものの依然として成年被後見人や被保佐人の方にとってはハードルが高いものと言えるでしょう。
同時に、成年被後見人や被保佐人でなくても精神機能の障害によって古物営業が適正になされないと判断されれば、許可を受けることはできないということでもあります。
刑罰や許可の取消し処分を受けて5年を経過しない者は古物商許可を取得することはできない!
過去5年間で、違法行為により刑罰を受けたことがある方や、以前取得していた許可を取り消されてしまったという方は、欠格事由に該当する可能性がありますのでご注意ください。
該当する刑罰
以下の刑罰を受け、その執行が終わってから、または執行猶予により執行されないことがなくなった日から5年を経過していない者は、古物商許可申請をしても不許可となります。
- 禁錮以上の刑
- 無許可営業による罰金刑
- 虚偽申請による罰金刑
- 名義貸しによる罰金刑
- 公安委員会の命令に違反したことによる罰金刑
- 窃盗罪による罰金刑(H30年10月追加)
- 背任罪による罰金刑
- 遺失物等横領罪による罰金刑
- 盗品譲受け等による罰金刑
禁錮以上の刑
禁錮とは、刑務所に拘留して自由をはく奪する刑罰のことです。懲役と違い、刑務作業を行う義務はありません。
禁錮以上の刑とはどんな刑罰か?という疑問がありますが、一般的に「死刑、懲役、禁錮」と考えられています。
執行猶予は、あくまで猶予であって免除ではありませんので、例えば「懲役6ヶ月、執行猶予3年」の場合、執行猶予がついていますが禁錮以上の刑に該当します。
許可の取消し
次のような行為を行い、公安委員会から許可の取消しをされた者は、取消しの日から5年間は古物商許可を受けることはできません。
- 古物営業法関係の法令違反、古物営業についての他法令違反において盗品等の売買の防止もしくは盗品等の早期発見が著しく阻害されると認めるとき。
- 古物営業法に基づく処分に違反したとき。
なお、下された取消し処分に対する不服申し立てをした場合で、意見陳述の期日と場所が指定された日から結論が出されのるまでの間に、古物営業の廃止を理由とした許可証の返納をしたとしても処分を逃れることはできず、その返納した日から5年間は古物商許可を取得することはできません。
暴力団員や犯罪組織の構成員は古物商許可を取得することができない!(平成30年10月追加)
暴力団員や犯罪組織の構成員は、古物商又は古物市場主に課せられた各種義務の適切な履行を期待できないことから、平成30年10月24日の改正で欠格事由が追加されました。
なお、この規制は改正前に許可を受けた者も対象となります。よって、これまで古物営業が認められていたとしても古物商許可等をはく奪されるということになります。
また、法律の文言には出てこないのですが、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者も含まれることに注意が必要です。
住んでいる場所が不明な場合は古物商許可を取得することはできない!
古物営業は盗品を売買してしまうリスクがあります。そして、古物営業法は「防犯」と「被害の迅速な回復」を目的としています。したがって、どこの誰か分からない者に古物営業をさせるわけにはいきません。
たまに法人の場合で、役員が会社所在地に住民登録をして実際は別のところに住んでいるという方がいらっしゃいます。
住宅兼事務所であれば大丈夫ですが、住んでいないことが明らかな場合は欠格事由に該当し、許可されませんのでご注意ください。
この場合、住民登録を正規の住所に変更するか、正当な理由を述べた理由書の提出が必要となります。なお、税金逃れなどの理由は正当な理由にはなりません。
未成年は法定代理人の許可なく古物商許可を取得することはできない!
原則として、未成年者は売買契約などの法律行為をすることができないため、古物商許可を受けることはできません。
しかし、法定代理人(親権者、未成年後見人など)の許可を得ることができれば古物営業をすることができるようになります。つまり、古物商許可の取得も可能になります。
民法6条1項
- 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
法定代理人とは?
法定代理人とは、法律により本人に代わって各種契約などの行為を行うことができる権限を与えられる者のことで、例えば、未成年の親権者や成年後見人などが法定代理人にあたります。
例えば、未成年が携帯電話の契約を本人でする場合に親の委任状を求められるのは、法定代理人の許可が必要だからです。
法定代理人の許可がなくても古物商許可を取得できる場合がある!?
上記の通り、原則として未成年は法定代理人の許可なくして古物営業を行うことはできません。しかし、一定の要件を満たすことで法定代理人の許可が無くても古物商許可を取得することができるようになります。
一定の条件とは以下のようなものです。
- 未成年者が古物商または古物市場主の相続人であること。
- 法定代理人が欠格事由に該当しないこと。
例えば、両親を失った未成年者が、古物商であった親の事業継承する場合は、法定代理人の許可は不要になるということです。
なお、許可自体を継承することはできませんので、この場合は未成年者による新規の許可申請が必要となります。
管理者が欠格事由に該当する場合は古物商許可を取得できない!
管理者とは、古物営業を行う各営業所に必ず1人選任しなければならない古物営業の責任者のことです。
古物営業の責任者という立場上、欠格事由に該当していると許可を受けることはできません。
例えば、同一都道府県に複数の営業所を持つ個人や法人は1つの許可で古物営業が可能になります。 しかし、実際に古物を取引する営業所や古物市場において、まったく知識のない者が古物営業をすることは、盗品の流通を見過ごしてしまう可 …
古物商の管理者についてよくある質問をまとめてみました。 Q1.家族経営で古物商をしてます。経営者自身が古物営業を管理する場合でも管理者の選任が必要ですか? A.はい。必要です。 経営者が自ら古物営業を管理する場合でも、管 …
法人役員が欠格事由に該当する場合は古物商許可を取得できない!
法人においては、代表と管理者だけでなく役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。
したがって、法人が古物商許可申請をする場合は、添付書類として役員全員が欠格事項に該当しない旨を証明する書面を提出することになります。
前回の記事では、個人申請の場合に必要となる書類をご紹介しました。 法人名義で古物営業を行う場合は法人を申請人として許可申請を行う必要があります。 今回は、法人申請の際の必要書類を列挙していきます。個人申請に比べて記載事項 …
まとめ
いかがでしょうか?
結果としてかなりのボリュームのある記事となってしまいましたので、一度読んだだけではなかなかご理解していただけないかもしれません。しかし、許可申請においては極めて重要な部分ですから、しっかりと読破していただければと思います。
普段から平穏に生活している方であれば、まず欠格事由に該当することはないと思いますのでご安心ください。
参考にしてみてください。




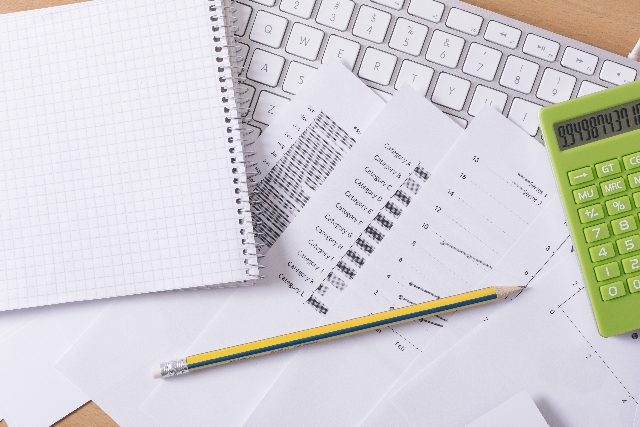





メールで完結!個人申請が好評です!
愛知県の古物商許可申請なら
愛知古物商許可.comにお任せください!
愛知県の古物商許可申請代行サービスをご利用いただけます。
面談不要!メールのやりとりだけで簡単に古物商許可が取得できます。(FAX・郵送でもOK)
メールで完結するから忙しい方におすすめ。特に平日は仕事をされている個人様から好評です!もちろん法人申請も対応可能!
<古物商許可申請>
ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ!